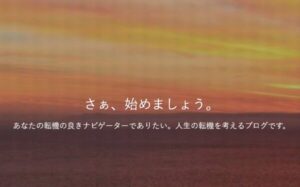村上春樹さんの中編小説「色彩を持たない多崎つくると彼の巡礼の年」が発表された2013年4月は、ちょうど今から10年前。村上春樹さんは64歳、作中の多崎つくる君は36歳で、魅力的な彼の恋人、沙羅は38歳。
それから10年経ったこの4月、村上さんは新作長編小説「街とその不確かな壁」を発表しました。
その新作を読み終えた後に、再び「色彩を持たない多崎つくる(以下省略)」を読み返してみました。
これは多崎つくる君を軸とした転機についての物語です。
多崎つくる君が19歳から20歳になる頃、彼は死の淵に瀕しました。理由もわからぬまま高校時代の仲間たち4人から絶交を言い渡され、精神的に瀕死の状態で数か月を過ごした過去が描かれます。やっとのことで生の世界に戻り、なんとか現実に適応するように努め生きてきました。
そして36歳になった多崎つくる君の前に魅力的な女性、木元沙羅が現れます。沙羅の計らいによって、ここから旧友たちを巡る彼の旅がはじまります。「死と再生」を乗り越えて、成長のための通過儀礼としての旧友との再会が描かれていきます。
まだこの小説を読んでいない方に対して、この小説を読む喜びを損なってしまわぬようにしなくてはなりません。一方で、すでにこの小説をお読みになった方には、この記事がこの本を再読するきっかけになってくれたならうれしく思います。
私はこの小説を語り過ぎないようにと留意しつつ、この文章を書いています。それでは何を書いてみたいのか?あなたに何をお伝えしたいのか?を明らかにしますね。
村上春樹さんのこの小説「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」をテキストとして、「転機」にフォーカスしてみたいのです。
この小説を初めて読んだ十年前、私はキャリアカウンセラーとして仕事を始めたばかりで、同時にウィリアム・ブリッジズの「トランジション 人生の転機を活かすために」も読み終えたばかりの頃でした。そのタイミングで「色彩を持たない多崎つくる」君に私は出会ったのです。東日本大震災の後に生み出された日本文学の中で、最も美しい小説であると感じました。
そして同時に、この小説には、村上春樹さんの「転機」に対する深い思索と思いが反映されているように受け止めました。その意味でも感銘深かったのです。それから何度もこの小説を読み、ラインマーカーで線を引き、それはカラフルな本になりました。
この記事はこの小説における「転機」にスポットライトを当ててみる試みです。
□
多崎つくる君は恋人の沙羅に、高校生の仲間たちを「乱れなく調和する共同体」(P20:引用)と表現しました。名古屋の高校の四人の仲間たち、青海悦夫(おうみよしお)、赤松慶(あかまつけい)、白根柚木(しらねゆずき)、黒埜恵理(くろのえり)。
最初に読んだ時、多崎つくる君の「転機」の深刻さが強く印象に残りました。脇役として配置されたはずのこの四人の人生に思いを馳せる余裕はなかったように思います。
しかし繰り返し読むうちに、つくる君とは異なる人生のタイミングで、四人はそれぞれ無数の「転機」に翻弄されてきたことがわかるようになりました。
例えば、アカ(赤松慶)は十六年後の現在、名古屋でBEYONDというビジネスセミナー会社の経営者になっています。高校を卒業し名古屋大学経済学部を卒業して大手銀行(メガバンク)に入行したものの三年で退職し中堅のサラ金会社へ転職。そこも二年半で辞めて起業し現在に至っています。
このキャリアが順調なものではなかったことが、後に本人から多崎つくる君に語られることになります。そして内面の吐露を聴くことができます。痛みを伴う何かをつくる君は受け止めます。
例えば、クロ(黒埜恵理)は現在、陶芸家としてフィンランド人の夫と共にフィンランドに住んでいます。高校を出て名古屋の私立女子大英文科を卒業したものの、後に愛知県立芸術大学工芸科に入り直し、そこでエドヴァルト・ハアタイネン氏と恋に落ち結婚。今ではフィンランド国籍を持ち、日本には帰らないと考えています。クロもまた痛切な何かを多崎つくる君に吐露します。
アオ(青海悦夫)も例外ではありません。例外なくシロ(白根柚木)もまた。

一方で、多崎つくる君は東京の大学に進学しました。大学2年の夏から始まる深刻な「転機」を経て工科大学の土木工学科を卒業し、首都圏西部をカバーする私鉄会社の施設部建築課課長代理として駅舎の設計管理をしています。
専門職として十四年間勤務し、自らその仕事を「天職」と思い、一見破綻のない人生を歩んでいるようにみえますが、その内面の痛み、内省の思いを読者は受け止めます。しかも多崎つくる君の「転機」は実は本当は終わっておらず、それゆえに巡礼の旅を勧める沙羅の言葉に従う彼がいるのです。
そのようなことに気づいてきて、それぞれの人生にそれぞれの痛みがあり、その最も痛切な痛みに実は全員がつながれているということを、多崎つくる君は学んでいくのです。痛みは自分だけではないということを。
2013年5月6日に村上春樹さんが京都で行った「公開インタビュー」の新聞記事を十年前の私は読んでいました。
「魂を観る、魂を書く」と題されたその記事が読売新聞夕刊(5月7日)に載りました。そこで村上春樹さんの重要なコメントが紹介されていましたので、ここに引用します。
『僕も、こんなにひどい経験ではないけれど、似たような経験をしたことがある。(中略)でも人は心に傷を受けて、心をふさいで、時間の経過と共に一つ一つ心を開いて、上に行く』
人生はその繰り返しで、結局そういう物語を書きたかったんだと思う、と振り返ったとありました。
同日の日経新聞夕刊の紹介記事の見出しは、『新作執筆は「人間への関心」』。それを引用します。
『人間と人間のつながりに強い関心がある』とし、『「人間への関心」が主人公の高校時代の友人たちを詳しく書くことにつながった』と明かしたとあります。そして『一切手抜きすることなく小説を書いてきたのが僕の誇りです』と締めくくったとありました。
□
「転機」は容赦なく登場人物たちを飲み込み、蝕み、彼らの人生を翻弄し、そして生き残った者たちはそれでも生きていこうとする物語。
それが私にとっての「色彩を持たない多崎つくると彼の巡礼の年」です。
2013年4月に、発売されたばかりのこの小説を読み終えて、「この時代にうまれた最も美しい小説のひとつ」と感じました。そこにはしかし「ほのかな希望の光」があり、「人は人に対して少しは優しくなれるに違いない」と感じる自分がいました。それから十年経ってもその思いは変わりません。そして折に触れて私はこの本を再読してきました。
それはどうしてなのでしょう?
きっとそれは「転機」を巡る目の前の相談者(クライエント)と共にありたいと願っていることと無縁ではないのでしょう。
イエローやグリーンのラインマーカーで彩られたカラフルな「色彩を持たない多崎つくると彼の巡礼の年」。
きっとこれからももっとこの本はカラフルになっていくに違いありません。
そしておそらくこれからも、多崎つくる君とその仲間たちのことを考え続けていく自分がいると思います。