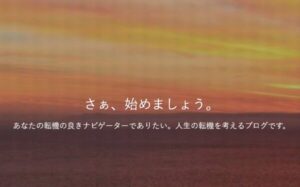映画「フェラーリ」を観に行った方で、これは自分の観たかった映画とは違う・・・そんな感想を抱いた方は少なくないと思います。TVCMでは、大惨事で最後となった1957年の「ミッレミレア」の迫真のレースシーンが中心です。しかし映画評を読んでみると半分位の人は映画に違和感を覚えているようでした。
一言でいえばカタルシスを期待して観ると裏切られる映画かもしれません。そこには複雑な夫婦間のデッド・ヒートが繰り広げられているのでした。
映画が描くのは、今日のフェラーリの礎(いしづえ)を築き上げたエンツォ・フェラーリの1957年の僅か3ヶ月の物語です。妻(ペネロペ・クルス)との葛藤を軸にしたファミリー・ドラマです。映画の最後のテロップから逆算すると、今日あるフェラーリ社とフェラーリ一族のドラマという捉え方もできるでしょう。映画の最後、妻(ペネロペ・クルス)の動じない瞳は、ずうっと私たちの心に残るものでした。
今年81歳になった監督マイケル・マン。彼はフェラーリ一族そのものを描きたかったのだと思います。映画という娯楽をわかっているマイケル・マンにとって、それは冒険であったに違いありません。家族の、そして夫婦の葛藤と悲劇にはカタルシスはありません。深い悲しみをひきずって生きていったエンツォもその妻も、フェラーリの栄光の陰で生きたのです。
マイケル・マンは私の大のお気に入りの映画監督です。なので贔屓目に映画「フェラーリ」を観ました。なにしろ、マイケル・マンの監督した「ヒート」(1995)から、私は彼の全監督作品を観ています。
「ヒート」(1995:Heat)、「インサイダー」(1999:The Insider)、「ALI アリ」(2001:Ali)、「コラテラル」(2004:Collateral)、「マイアミ・バイス」(2006:MIAMI VICE)、「パブリック・エネミーズ」(2009:Public Enemies)、「ブラックハット」(2015:Blackhat)、「フェラーリ」(2023:Ferrali)。この8作品が、52歳から80歳までに彼が監督した作品すべてです。
そのすべてに彼の映画づくりにかける「情熱」がみなぎっています。そして彼の描く主人公は、Too much(やり過ぎ)な男が多いのです。エンツォはその系譜にしっかり位置づけられます。しかし広告やCMで語られるような「狂気」というものではなく、ビジネスマンとしてフェラーリを守り、家族を愛し、しかし複雑な夫婦関係をどう制御していいのかわからないまま維持している男です。まれに気弱でダメなエンツォの眼差しが私の印象に残りました。また息子に語りかける父親の姿、フェラーリにかけるエンジニアとしての誇りは、胸を打ちます。
フェラーリ社創業者である主人公エンツォ・フェラーリ、59歳。その直面した人生の最大の危機的状況が描かれます。
プロモーション映像がYouTubeに沢山あがっています。その中から、マイケル・マンがこの映画につぎ込んできたパッションをもっとも感じられる動画を3つ選んでみました。メイキング映像には、現場で生き生きと監督するマイケル・マンの姿がしっかり刻まれています。
マイケル・マンの言葉から、「神は細部に宿る」という言葉を思い出しました。
エンツォの情熱、演じるアダム・ドライバーの情熱、映画を創造するマイケル・マンの情熱がつながっています。
繰返しますが映画「フェラーリ」はカーレースの物語ではなく、エンツォのファミリー・ドラマ、悲劇的な一族の物語です。
(ここから先はネタバレになります)
1957年、イタリアの自動車メーカー、フェラーリ社の創業者、エンツォ・フェラーリ(59)は、会社経営と私生活の両方で危機に瀕していました。エンツォは元レーサーで、今はフェラーリ社の経営者として社の存亡に直面しています。しかし愛する息子を亡くし妻との関係も冷え切り、会社は倒産の危機に瀕します。そんな中エンツォは再起を賭け、イタリア全土を走る過酷な公道レース「ミッレミリア」に挑みます。フェラーリ社を存続させるためには挑まないという選択肢はもはやなかったのです。
監督マイケル・マンは、フェラーリ一族と長年の交流があり、原作出版時からこの映画化を熱望していたそうです。30年来の念願の映画化だと伝えられています。主演のアダム・ドライバーは、エンツォになりきるために外見だけでなく、身のこなしや話し方も徹底的に研究。エンツォと彼を取り巻く女性たちとの複雑な関係、そしてライバルであるマセラティとの熾烈な争い。特に「ミッレミリア」のレースシーンは当時の空気感を再現するため、特殊な車載カメラやドローンを駆使し撮影されました。そしてあの目を覆うばかりの大惨事・・・。1957年のわずか3ヶ月に集約されたエンツォを取り巻く物語。
エンツォ・フェラーリの孤独。成功への渇望。どうしようもない家族間の葛藤。矛盾に満ち満ちたパッション・・・。そして私にとっては、それらを描く監督マイケル・マン自身の《映画をつくるというパッション》が投影された作品として、この映画「フェラーリ」を捉えました。
1957年は、エンツォ・フェラーリにおいてまさに人生の転機の年でした。そのわずか3ヶ月に集約されたエンツォの人生。その物語。そこであるいはフェラーリ社は終わったかもしれない。その中をエンツォは生きたのでした。愛する息子の死。レーサーたちの死。子供を含む観客9人の死。それらに対しても心の防御壁で身を守ろうとしながら。
この映画「フェラーリ」、実は81歳の現役監督マイケル・マンこそ真の主人公なのです。少なくとも私にとっては。
マイケル・マンにしか描けなかった映画、それが「フェラーリ」です。