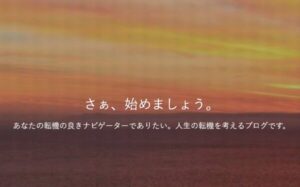私たちは、自分の「心」をどのように捉えているでしょうか?フロイトの呪縛から解き放たれているでしょうか?
この『心はこうして創られる 「即興する脳」の心理学』(講談社選書メチエ 2022.7発行)を読んで、私は今までなんとなく信じていた「心」の在りようとは、全く異なる在り方を突き付けられた感じがしました。
著者は、認知科学の理論家として知られるニック・チェイター教授(英国 ウォーリック大学)です。まず英国とアメリカで発売され、次にフランス語、スペイン語、中国語にも翻訳され、アメリカ出版協会PROSE賞(臨床理学部門 2019)を受賞しています。ひと言でいうと、心の分野で「天道説」から「地動説」へのコペルニクス的転回を迫るような刺激的論考です。
カウンセリング領域に関わる人にとっては必読書でしょう。「天動説」の世界で今まで通り仕事することをよしとするなら別ですが。コーチ業やキャリアカウンセラーの方にもお勧めしたいです。
原題は「マインド・イズ・フラット:心の深さと即興する心」。
THE MIND IS FLAT : THE ILLUSION OF MENTAL DEPTH AND THE IMPROVISED MIND
心の表面(意識的に自覚できる思考や感情や知覚)が心のすべてであり「心の奥の思考や感情や知覚」など存在しない(p320)と翻訳者は説明します。
本の帯にあるフレーズは超刺激的です。
あなたが「思っている」と思っていることは、全部でっち上げだった!
カヴァーの裏面にも挑発的な文章が記されています。
無意識の思考や深層心理や内的世界。そんなものは存在しない。すべては脳の即興=瞬間的にでっち挙げているものだった!
チェイター教授はこの著書の中で「脳は、倦むことのない迫真の即興家」であり、「あまりに説得力ある物語作者(ストーリーテラー)」であると繰り返し繰り返し述べています(P307)。
「内観という処理(プロセス)は、何かを知覚しているのではなく、創作している。自分自身の言葉や行動の意味をとるために、リアルタイムで解釈を生成しているのだ。内なる世界、それは蜃気楼にすぎない」(P11)。
精神分析理論をうち立てたジグムント・フロイトのいうイド・自我(エゴ)・超自我(スーパーエゴ)、ユングのいう集合的無意識もまた、まったくのデタラメだと言い切ってしまう(P16)チェイター教授は、エキセントリックな異端児ではありません。認知心理学の研究者として科学の本流にいます。
「ここ数十年の人工知能研究のある種の失敗」(P315)から、この考え:THE MIND IS FLATへとたどり着いたということです。
私は、この本を読むまでは、自分の心の中に「内なる世界」があるものと信じていました。しかし本当はそのようなものはなくて、絶えず心の表面でストーリーを創作しているのだとしたら?今まで信じてきたものがデタラメにすぎないとしたら?・・・私は、この本を読んで、自分の「心」の理解をもう少し深めるべきだと思いました。
勉強しなくてはなりません。
□
私の経験したカウンセリングの研修で、このような場面がありました。カウンセリングのスキルをあげるための研修で、このようなカウンセラー役の問いかけから始まります。
「幼年期、そうですねぇ 5歳位までの記憶の中で、何か辛かったこと、あるいは悔しかったことはありませんか?」
「う~ん そうですねぇ 幼稚園の頃、ですか? 幼稚園の頃・・そういえば幼稚園の頃に・・・なことがありました。とても痛かったので、よく覚えています」
「その痛かったことから、どんな教訓というか、学びがありましたか?」
「そういえば、高校の時にも同じように・・・」
自分がクライエント(相談者)役をしていて、自分の脳が相手のカウンセラー役の方を密かに助けるために、その場で思いついたエピソードをネタにして、その後の展開を創作していった・・・そんな感じです。そのような自分の心の動きを、私自身感じ取っていました。
カウンセリング研修の話の辻褄(つじつま)を合わせるように、ふるまっている自分がいました。
心はサービス精神が旺盛で創造的です。一瞬にして、まことしやかな話をでっちあげています。そんな自分がその研修場面において確かにいました。その私の心のサービス精神は、カウンセラー役の方が学びを深められるよう、提供するネタを用意してあげたいという善意であり、学び合うふたりの関係性が損なわれないようにしようとする人間的配慮でもありました。
幼年期のエピソードは、決して潜在意識や無意識から浮かび上がってきたものではなく、トラウマでもなく、無数にあるであろう記憶の海の中から、たまたまその時浮かんできた欠片(かけら)を述べたにすぎません。他にあげろといわれれば、他のエピソードをあげることができました。しかも巧妙なことに私の脳は、全体の研修テーマに当てはまるようなエピソードを選んで提供しているのでした。
クライエント役とカウンセラー役が、共同で創作活動をすることに、どのような価値があるのか?今の私にはわかりません。しかし無数のストーリーを描くことができるだろうということだけは確信をもって言えます。
このようなカウンセリングが実際に行われたとして、それがどのような価値ある意味を相談者(クライエント)に提供できるでしょうか?
一緒になって、望ましいストーリーラインを描いていくことは、ある解釈にすぎないかもしれません。ストーリーAがあるならば、ストーリーBもCもありえます。
□
20世紀初頭のウィーンの街中でのことです。後に著名なオペラ監督となるハンス坊や(4歳)は母親との散歩中に恐ろしい出来事に遭遇しました。大型の馬車の馬一頭が倒れ、激しくもがき苦しみだしたのです。それをみて震え上がったハンス坊やは、すっかり馬を恐れるようになりました。心配した父親は地元の医者に相談しました。当時流行していた精神分析理論に従って、ハンス坊やは「実は小さなオイディプスだ」と見立てられました。幼年期に短期間生じたこの恐怖症を、そのように見立てた地元の医者の正体は、ジグムント・フロイトその人でした。(P121~125)
ニック・チェイター教授は、その誤りは「文学的創作と心理学を混同したこと」と捉え、心理学を科学としてではなく「文芸の一形態として実践してしまった」と論じています。
20世紀初頭から120年以上経過しても、偉大なるフロイトの著作の影響の裾野は広く、あらためて私もまたフロイトの影響下にあったのだと気づいたのです。ハンス坊やの潜在意識的な内なる心の世界は、そもそも存在していないのに、一生懸命覗き込もうとしていたのですから。
『心はこうして創られる 「即興する脳」の心理学』はそのようなことを私に教えてくれました。再読したくなる労作です。
私たちが学ぶのは、人間を真の意味で正しく理解するために他なりません。私もまたそのうちの一人なのです。